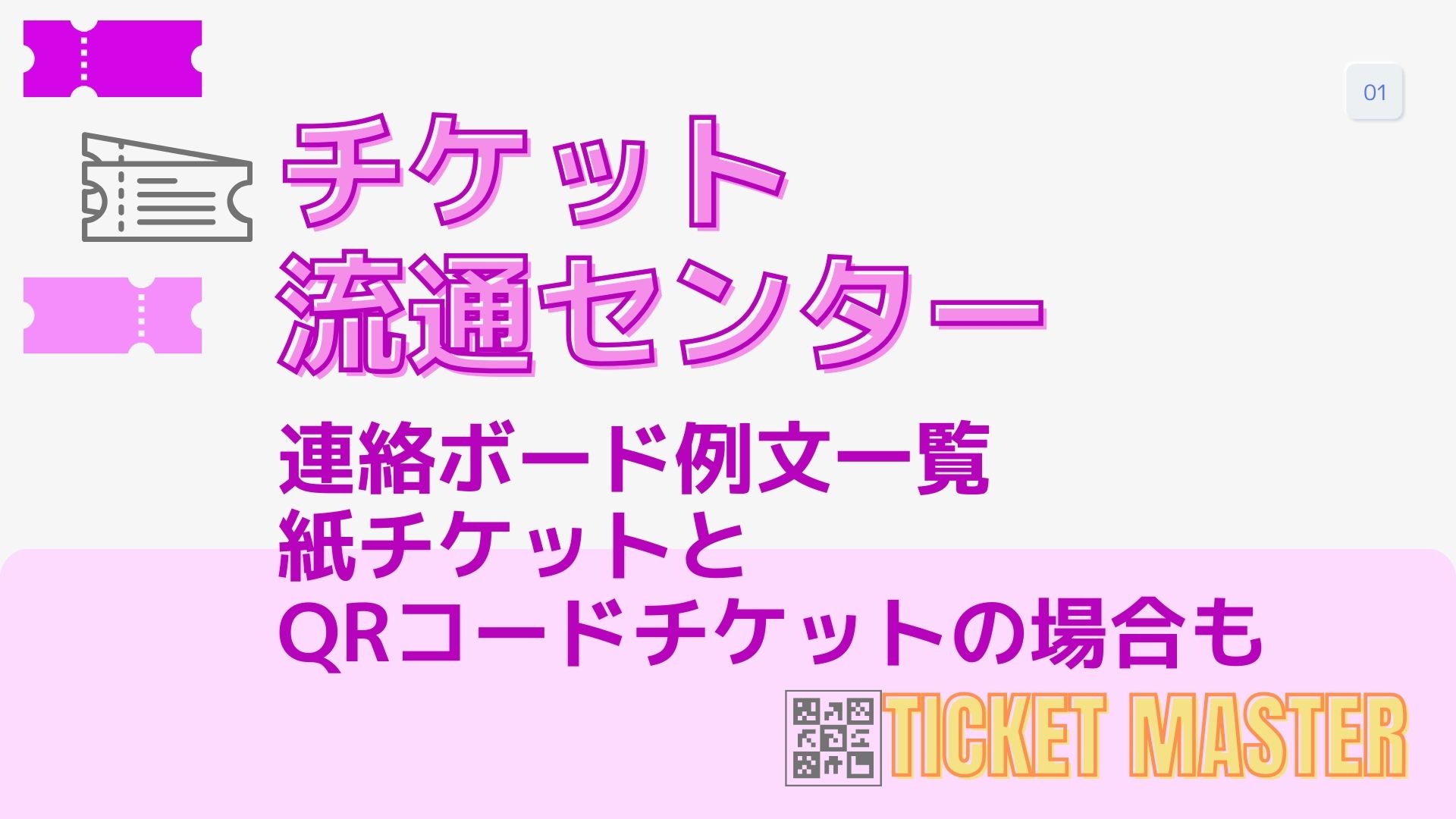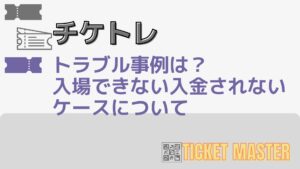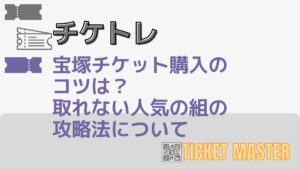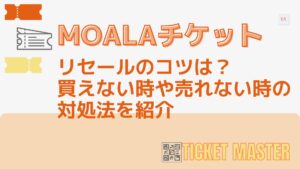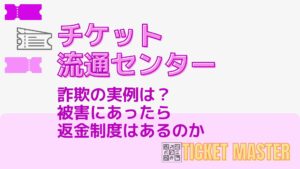イベントやコンサートのチケットの購入や販売で連絡ボードというシステムがあります。
チケット流通センターの連絡ボードを使ったことはありますか?相手にどんな文章を送ったらいいのか考えたことはありますよね。相手に失礼がないか、大丈夫かなと不安になったことはあると思います。
この記事を読まれている方はこのような疑問をお持ちではないでしょうか?

連絡ボードに載せる例文があったらいいな
紙チケットとQRコードで使える例文を知りたい
- 連絡ボードを使ってのやり取りは可能か
- チケットによって簡単に使える例文はあるのか
チケットの売買取引なら
「チケジャム」がおすすめ!
不正取引の対策&代金一時預かりとチケット入場補償サービスありで安全に取引ができますよ。
\チケット購入でポイント10%還元 /
チケット出品者は出品者は手数料無料
チケット購入者は取引手数料実質無料
チケット流通センター連絡ボードの使い方手順
郵送や郵便での取引をしない場合は、連絡ボード機能で取引を行うことができます。
連絡ボードは、「電子チケット・発券番号・受け渡し指定・同行募集」で買い手の入金が確認された後に取引画面に表示されます。入金が確認される前は表示されません。
「郵送・宅配便」の取引では連絡ボードは使用できません。
先述したように売り手と買い手両方ともに連絡ボードは、
チケット流通センターで買い手からの入金確認が取れた後に連絡ボードが使用可能
分かりやすく連絡ボードの使用タイミングと取引の流れを紹介します。
※チケット流通センター マイページはココからどうぞ
下の画像のように入金確認の連絡がチケット流通センターの運営から届きます。
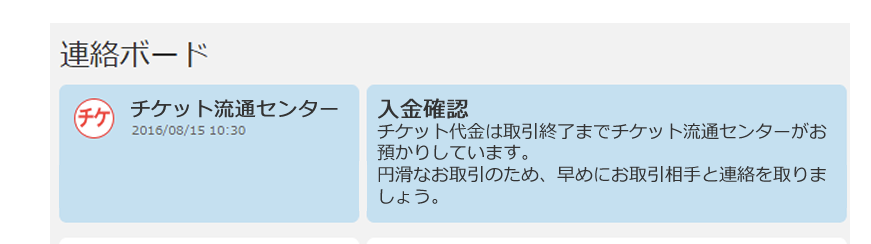
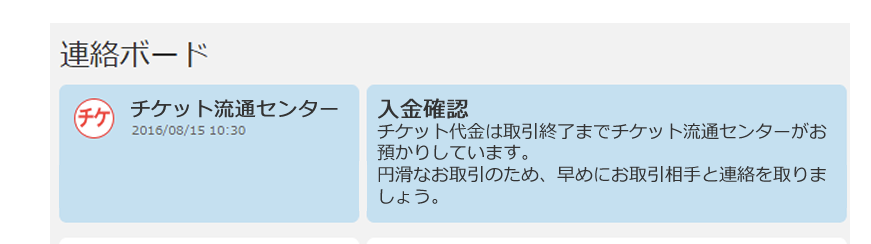
相手への挨拶やお礼・伝達事項などメッセージを入力しましょう。
※必要な場合は画像の添付なども行われます。


メッセージの例文は、事項にて詳しく紹介するので参考にしてみてくださいね。
※受け取り時に発券手数料がかかる可能性があります。
※売り手側への受取完了連絡は忘れないようにしましょう。
※連絡をしないと売り手が無事に受け取れるのか不安になります。
※受取完了連絡はチケット確認後すぐに行いましょう。
上記のように取引の流れの中で、必要事項や受取完了などのを連絡ボードを使ってやり取りします。
連絡内容を何日もしないまま返信を放置しないようにこまめに確認するようにしましょう。
連絡ボードでのやり取りは、すぐに早めに対応することが大切です。
チケット流通センター連絡ボード例文①紙チケットの場合
チケット流通センターで連絡ボードを使用する際、どんな文章を相手に送れば良いのか迷ってしまいますよね。
ここでは紙チケットの場合に連絡ボードで送る例文を紹介していきます。
前提として紙チケットを連絡ボードでやり取りするケースは、
・発券した紙チケットを「受渡し指定・同行募集の場合で、受取・同行の手段・日時や場所決めを連絡ボードにてやり取り
・チケットが発券前の状態で「発券番号」を連絡ボードを使用して買い手に教える
上記の2通りのケースにて、連絡ボードを使用したやり取りが必要となります。
「郵送・宅配便」の取引では連絡ボードは使用しません。
では気持ちのいい取引をお互いに進めるために、2通りのケース別に買い手と売り手それぞれの例文を紹介します。
受渡し指定・同行募集の場合
紙チケットの受渡し指定・同行募集とは、
受渡し指定:売り手が指定した方法でチケットを受け渡す取引(公演3日前から利用可能)
同行募集:売り手が同時に入場することを確約する取引
上記の取引内容となります。
ですので文章で大切となるポイントは売り手側の、
受け渡し方法、日時、場所を詳しく記載
以上を忘れずに記載しましょう。
では買い手側に大切なのは、
これは売り手買い手双方に言えることですね。お互いが安心し合える取引を心がけましょう。
では例文を売り手買い手それぞれ紹介します。
売り手の例文
まず受渡し指定を郵送にした場合、
はじめまして。
この度は、お取引いただきありがとうございます。
こちらのチケットは、○月後半(詳しくわかる場合は日付を記載)に届く予定です。
確認でき次第ご連絡いたします。
また、発送が遅れる場合も再度ご連絡させて頂きます。
お取引完了まで、どうぞよろしくお願いします。
届く日時や時間帯の記載は忘れず、なるべく詳しく記載してあげると買い手の安心度は上がりますよ^^
チケット流通センターの利用が初めてや、まだ不慣れで心配な場合、
こういった取引が初めてなので、対応など不備があれば教えていただけると幸いです。
初めての利用で取引が不慣れです。
何か説明不足など不備がありましたら、遠慮なくお聞きください。
上記のような文章を添えておくのも印象は良いでしょう。
受渡し指定を直接にした場合、
はじめまして。
この度は、お取引いただきありがとうございます。
受け渡しに関しては、〇〇(場所)に〇時にてお渡しを考えております。
ご都合はよろしでしょうか。
時間や場所についてのご希望や要望ございましたら、気軽におっしゃってください。
お取引完了まで、どうぞよろしくお願いします。
売り手側が受け渡し方法や場所日時を決めて行う取引です。
しかしあまり一方的な文章になりすぎないようにしましょう。
相手の都合考慮している旨を一言添えると印象は良いものになるでしょう。
次に同行募集の場合は、
この度は〇〇チケットのご同行募集にお声がけいただきありがとうございます。
最後まで責任をもってお取引させていただきます。
こちらが所持しておりますチケットは、(○月○日××時開演などチケットの詳細を記載)のチケットでございます。
当選画面も添付致しましたので、お間違いないかご確認よろしくお願いいたします。
公演当日ですが、開演時間よりも余裕を持って、〇時待ち合わせでいかかでしょうか。
場所は会場の〇〇(会場付近の分かりやすい場所)ではどうでしょう。
ご連絡お待ちしております。
長文となり申し訳ございません。
お取引終了まで何卒よろしくお願いいたします。
上記のような文章はいかがでしょうか。
同行募集へのお礼・当選している事を証明できる画像添付・当日の待ち合わせ場所と時間の提案は最低限記載したほうが良いでしょう。
必要事項を比較的簡潔にまとめるのがポイントとなります。
待ち合わせに関しては相手の返信をみて、双方無理のないような場所と時間を話し合って決めていきましょうね。
その後場所や日時が決まった場合、
ご連絡ありがとうございます。
では会場の〇〇(場所)に〇時でお待ちしております。
当日待ち合わせ場所に到着しましたら、こちらの連絡ボードにて連絡いたします。
何かご不明な点やご心配なことがありましたら、いつでもご連絡いただければと思います。
当日はよろしくお願いいたします。
最終的な場所と日時を確認したら当日を迎えるだけです。
買い手からどんな連絡があるか分からないので、当日の取引終了までは連絡ボードはこまめにチェックするのを忘れないようにしましょう!!
買い手の例文
受渡し指定・同行募集の場合の買い手は基本、
売り手が指定した方法でチケットを受取る
それを踏まえて例文を紹介します。
受渡し指定が郵送の場合、
はじめまして。
貴重なチケットをお送りいただきありがとうございます。
チケットが確認でき次第、すぐに「受領完了連絡」をさせていただきます。
お取引完了まで、どうぞよろしくお願いします。
その後チケットを無事受け取れたら、
本日無事チケットを受取りました。
受取完了の連絡をさせていただきます。
お取引いただきありがとうございました。
受取完了の連絡は確認後すぐ行いましょう。
受渡し指定が直接・同行募集の場合は、
はじめまして。
チケット受け取りの待ち合わせは、〇〇(場所)に〇時で問題ありません。
待ち合わせ場所に到着しましたら、こちらの連絡ボードにてご連絡します。
こちらこそお取引完了まで、よろしくお願い致します。
無事に待ち合わせ場所に到着しチケットを受け取った後、
本日はありがとうございました。
受取完了の連絡をさせていただきます。
お取引いただきありがとうございました。
簡潔にお礼と受取完了の連絡を入れれば十分でしょう。
同行募集の場合は、当日会場に入場出来たら「受取完了連絡」を入れましょうね。
さらに、
など公演終了後に一言お礼をいうと相手も喜ばれますよ。
金銭が関わる取引なので、相手が安心できるような文章を送りましょうね。
発券番号の場合
売り手がコンビニなどでチケットをまだ発券していない場合、「発券番号」を連絡ボードを使って買い手に送ります。
ですので売り手は必ず「発券番号」の記載を忘れないようにしましょうね。
売り手の例文
はじめまして。
この度は、お取引いただきありがとうございます。
チケット発券に必要な事項を記載しておきます。
チケットサイト:〇〇
発券番号:〇〇〇〇〇〇
電話番号:〇△〇-〇△△〇-△〇〇△
何かご不明な点やご心配なことがありましたら、いつでもご連絡ください。
お取引完了まで、どうぞよろしくお願いします。
チケット発券してもらう為の必要事項は忘れず記載しましょうね。
あとは買い手の「受取完了連絡」を待つだけですよ。
買い手の例文
売り手から「発券番号」など必要事項が記載されたメッセージが届きます。
ですので、
はじめまして。
発券番号のご連絡ありがとうございます。
チケットが確認でき次第、すぐに受領完了連絡をさせていただきます。
お取引完了まで、どうぞよろしくお願いします。
売り手からすると、きちんと発券できるか心配してしまいます。
発券番号をもらったら、早めに発券しチケット確認を行い受領完了連絡をしましょう。
チケット確認後、
お待たせ致しました。
無事にチケットの発券が出来ました。
受取完了の連絡をさせていただきます。
この度は貴重なチケットを譲って頂きありがとうございました。
チケット確認後は、お礼とチケット受取完了連絡をすぐに行いましょうね!!
以上が紙チケットの場合の連絡ボード例文となります。
重要なのは、
相手の素性が見えない中での取り引きになるので、丁寧かつスムーズなやり取りが必要。
一言付け加えるだけで不安や心配事を取り除けるような文章を使う。
以上のことを心がけてメッセージは送りましょう。
チケット流通センター連絡ボード例文②QRコードチケットの場合
QRコードをかざす電子チケットの取引は、売り手からサイトURLを送ってもらいます。QRコードをダウンロードして、チケットを提示します。
QRコード取引は、スクショ画像や会員番号などの個人情報を開示し取引することもあります。
主催元によっては、スクショ画像の使用や譲渡を禁止していることも多いです。必ず主催元の公式サイトを確認してください。
当日、発券時にチケットの確認ができたら、速やかに相手に受け取り完了連絡をしましょう。
売り手の例文
はじめまして。お支払いありがとうございます。
電子チケットは○月前半ごろに送付されてくる予定です。
確認できましたら、連絡ボードよりQRコードを送信いたしますのでダウンロードをして使用してください。
発送予定が遅れることがありましたら、再度ご連絡させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
QRコードを送信する場合の例文
お待たせしております。
QRコードが手元に届きましたので送信します。
○○様のスマホで開けるかどうかご確認ください。
よろしくお願いいたします。
買い手は「ちゃんと入場して公演が終わってから連絡しよう」と思う方がいるようです。
ですが、売り手からすると、「ちゃんと入場出来たかな?」など心配になります。
チケット流通センターは入場保証はしていません。チケットの確認ができたらすぐに受け取り完了連絡を行いましょう。
入場ができない場合は、チケット流通センターが売り手の情報を教えてくれるので直接交渉になります。「エラーで入れない」など不測の事態は自己責任となりますので、それを踏まえたうえでチケットの取引を行ってください。
買い手になったとき、チケットのすり替え防止策として会員番号の下3桁の聞き方の例文をお伝えします。
会員番号下3桁の聞き方例文
チケット詳細に記載がありましたが、念のため会員番号の下3桁のご提示を希望します。よろしくお願い致します。
「下3桁提示可能」の記載がない場合の聞き方例文
差し支えなければ、会員番号下3桁をうかがってもよろしいでしょうか?すり替え防止の為、教えていただけるとありがたいです。
まとめ
この記事では、チケット流通センターで連絡ボードを使用する際の例文等をまとめました。
- 金銭面が絡んでくるため安心した内容の文章を送ること
- なるべく迅速に対応すること
- チケットが届いた・受け取った、受取完了通知を相手に送ること
丁寧な対応をすることで相手も気持ちの良い返事をくれます。
人の第一印象は会った時で決まるといいますが、手紙や連絡などの文章も返事がいかに早いかどうかで決まると思います。
連絡ボードで何を書いていいかわからないときってありますよね。こちらをぜひ参考にしていただければと幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。